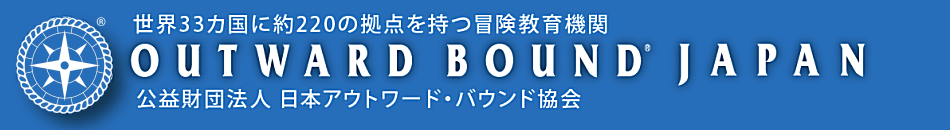ニュースレター文章作成の連絡が届いた時、400字程度に書いてくださいとお願いがありましたが、400字では収まりませんでした。
読みづらい文章で申し訳ありませんが最後まで読んでいただければ有り難いです。
 ▲デナリ
▲デナリ
標高6190m、気温-35度、ホワイトアウト、強風、クレパスなどデナリは厳しい自然環境であり多くの危険がある山。ポーターやガイド、山小屋などはなく、全て自分達の力で自己完結しなければいけない。
そんな環境の中、食料や装備が入った180リットルのダッフルバックをソリにつけて引きずり、100リットルのバックパックを背負って山を登って行った。キャンプ地は全部で5つ。1番上のハイキャンプ手前のキャンプ4まではソリに荷物をつけて引きずり、ハイキャンプ以降はバックパックのみでアイゼンピッケルを使い登っていった。
最も大変だったのは悪天候によりキャンプ4に2週間待機していた時だった。多くの登山隊は登頂を諦めて撤退していく中、僕たちは絶対に登頂するんだという強い気持ちで次の好天を待った。「いつまでここにいるのか?」という不安があるメンバーがいたり、食料やガソリンを他の隊に盗まれるというハプニングもあった。
2週間もの間、待機できたのは「イグルー」を作ったからだ。僕は青森大学時代に恩師である佐々木豊志先生にイグルー作りを教わり、今まで170基以上のイグルー作りに携わってきた。
2人用の山岳テントで2週間暴風に晒されながら待機するより、イグルーを作れば中で食事を作ったり、リラックスしてくつろぐ時間も確保できた。
イグルーがあることにより精神的なストレスが減り、生活の質も向上した。
キャンプ地での停滞期間を経て、山頂へ歩き出したチームは現地時間6/11 18時に9名全員到着した。
登頂した瞬間はみんな嬉し涙を流しており、山頂で喜びを分かち合った。
僕にとって「人生で1番嬉しい瞬間」であった。

▲デナリ山頂。メンバー全員登頂の喜びを分かち合う。
しかし、山頂は登山の工程の中での折り返し地点に過ぎず下山が1番リスクが高いため、改めて気を引き締めて下山をした。
僕は山頂からスキー滑走に挑戦するために、山頂までスキーを担いでスキーブーツで登っていた。
標高6190m、最大斜度55度、アイスバーンがある中、無数のクレパスを避けて滑走した。山頂から2000m地点まで2日間かけてスキー滑走をして下山した。
標高5500m辺りからは雪が良くとても楽しいスキーであった。
そして全員怪我なく、下山する事ができた。
今回の登山は悪天候もあり24日間の遠征になった。
今、主流のライト&ファーストの登山と逆行したヘビー&スローのスタイルは今回の様な不確実性が高い長期遠征にはベストのスタイルだと感じた。
デナリスキー滑走を終えて
デナリスキー滑走は僕の一つの夢であり、次のステージに上がるためのステップでもありました。
多くの人に応援•サポートしていただき一つの目標に到達することができました。
 ▲右奥レスキューガリーからスキー滑走
▲右奥レスキューガリーからスキー滑走
 ▲スキー滑走
▲スキー滑走
これまで、僕は何でも自分の力で乗り越えてやろうと思い取り組んでいましたが、人を頼ることでもっと大きな事ができるんだと実感しました。
僕1人の力ではデナリ登山のスタートラインにすら立つ事が出来ませんでした。応援してくれた皆さん本当にありがとうございました!
僕にとって今回の登山は、物質として人が一つの山に登った以上に大きな収穫がありました。自分自身で覚悟して決めた事を、強い気持ちでやり切った経験は大きな自信となり更なる可能性が見えてきました。
次は8000m峰に挑戦します。
これからも冒険は続いていきます。
最後まで読んで頂きありがとうございました!
みなさま引き続き応援よろしくお願いします!

▲イグルーの様子。中で煮炊きをするため熱気を逃がすために天井は特注タープを設置する。中央オレンジの帽子が喜來。

公益財団法人日本アウトワードバウンド協会
普及事業部 喜來大智
(キャンプネーム きらっち/Kirattchi)
山との出会い
大学2年の時、八甲田のバックカントリーガイドとの出会いをキッカケに八甲田バックカントリーガイドを始める。北東北、立山連峰、大雪山系、海外ではヒマラヤ「アイランドピーク」を含む6000-5000m級の山々5座を21日間で縦走する。
登山隊の概要
日本国内でガイド活動をする9名のチーム。隊長は富士山ガイドの「児玉Billy」さん、副隊長は白馬でバックカントリーガイドをしているプロスノーボーダーの「森亜希子」さん。顧問はデナリで気象観測を30年間続けてきた「大蔵喜福」さん。大蔵さんは植村直己さんをはじめとする多くの日本人がデナリで命を落とした事をきっかけに気象観測を始めた。今回の登山隊は大蔵さんが30年間続けてきたノウハウを伝授いただき実践した。